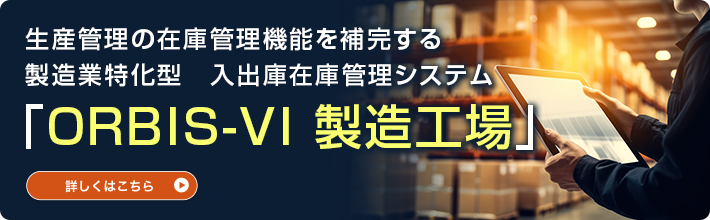物流業向け
キーワード
物流業におけるDX推進に関連した専門用語を解説します。
物流業向けキーワード
物流業におけるDX推進に関連した専門用語を解説します。
か行
クロスドッキング
クロスドッキングとは物流センターの仕組みを表す流通用語である。簡単に説明すると物流センターには多くの荷物がトラックで運び込まれるが、在庫することなく必要な荷物を仕分けして出荷する仕組みを指す。語源は、物流センターの荷受場所(ドック)から出荷場所(ドック)へ商品が交差(クロス)しながら仕分けや通過させることからそう呼ばれるようになった。
クロスドッキングの類似用語として「トランスファーセンター」がある。トランスファーセンターは荷物保管のない物流センターのことで、商品の開梱や検品などを行う。これに対してクロスドッキングは商品の開梱や検品は行わず、荷物の仕分けのみを行う。メリットは在庫を持たないため、大規模な保管場所や管理設備などが不要となり、この結果、設備利用費や人件費を削減することが期待できる。デメリットは荷物の入出庫情報を把握するため、高度な物流管理システムが必要である。この結果、初期投資が必要不可欠となる。
コールドチェーン
コールドチェーンとは商品を生産地から販売、消費されるまで一定の低温度(低温、冷蔵、冷凍)に保持した状態で流通させる仕組みである。別名で「低温物流」とも呼ばれている。コールドチェーンの歴史は古く、1925年頃、米国のアイスクリーム会社が冷凍車を導入したのが起源である。その後、1940年頃から同じ米国の物流業界で貨物を低温に保ったまま輸送する世界初のコールドチェーンが導入された。
日本は1959年、厚生省により、冷凍食品規格基準が告示された。これを期に物流業界はコールドチェーンが普及したと言われている。コールドチェーンのメリットは食品の鮮度維持が長期化できるため、流通段階での食品廃棄を大幅に削減することができる。またSDGs(持続可能な開発目標)という観点からもコールドチェーンの導入は企業イメージの向上に貢献できる。一方、生産や物流等の全工程で温度管理が必要になるため、多額の設備コストが必要となるのがデメリットだ。
さ行
サプライチェーンマネジメント
サプライチェーンマネジメントとは商品の生産や流通プロセスを最適化するための管理手法である。一般的にはSCMの略称で呼ばれており、「Supply Chain Management」の頭文字をとったものである。日本語訳は「供給連鎖管理」となる。SCMの歴史は古く、今から40年以上前の1982年に米国のコンサルティング会社である「ブーズ・アレン・ハミルトン」のK.R.オリバー氏とM.D.ウェバー氏がはじめて使ったとされている。たとえば、洋菓子店が原材料となる砂糖やクリームを仕入れてからショートケーキという商品を生産した後、顧客に商品を販売するまでの一連の流れを最適化させる取り組みである。
SCMは、この過程で業務改善や在庫管理の適正化等を実践することで企業経営の安定化を図ることで可能となる。近年はIT技術の進化により、容易にクラウド環境を使うことができるため、SCMを活用したITシステムがさまざまな企業で導入されて成果を上げている。
た行
棚卸
循環棚卸
循環棚卸とは在庫の種類や場所、作業日等を区別して行う棚卸手法である。別名で「サイクルカウンティング」とも呼ばれる。24時間稼働するコンビニエンスストアや製造工場では業務を停止することが困難なため、循環棚卸を採用し導入している企業ではハンディターミナルを活用して商品のバーコードやQRコードをスキャンする方法が主流である。これにより、全体の個数や変動も適時、データで一括管理できるようになっている。循環棚卸のメリットは、棚卸作業を少ない人員で行うことができるため、管理コストの負担が少ないことである。
一斉棚卸
一斉棚卸とは文字通り、業務を完全に停止して1日、2日間等の一定期間で一斉に棚卸を行う手法である。本手法は従来型の棚卸であり、信頼性の高い棚卸手法である。一斉棚卸のメリットは一度にまとめて在庫確認を行うため、正確で精度が高い。また事前に棚卸日が決定しているため、人の手配や作業時間等の計画も立案しやすい。
は行
ハンディターミナル
ハンディターミナルピッキングとは、読み取り機器である「ハンディターミナル」を使用した「ピッキング」を指す。ハンディーターミナルとは持ち運び可能な、バーコードおよびデータ読み取りをするための小型端末のことだ。ハンディターミナルには読み取ったデータを端末内に保存し、専用の台に乗せて倉庫内のパソコンへ転送するタイプと無線LANでどこからでもパソコンへデータが転送できる無線タイプの2種類が存在する。
このときの「読み取るデータ」とは、対象物の品質・在庫・追跡など入荷から出庫までの一連の状態を指す。
ピッキングとは、顧客からの注文や受注に応じて、倉庫内から対象の製品や部品を選び出すことである。ピッキング方法にも大きく分けて2つの種類があり、1つの梱包ごとに製品や部品をピッキングする「摘み取り方式(シングルピッキング)」と、複数の注文に応じるために、必要な製品や部品をまとめて倉庫内からピッキングする「種まき方式(トータルピッキング)」がある。ピッキングする際は、製品や部品に取り付けられたバーコードや識別番号を読み取って効率よく選ぶ必要がある。その際にハンディターミナルが読み取り機器として頻繁に利用される。
ピッキング
ピッキングとは伝票や指示書を元に必要な品物を倉庫内などで集める作業のことである。語源は英語の「Picking」で日本語にすると「摘み取る」、「採取」と訳される。ピッキングの種類は以下の2つに区別される。
シングルピッキング
受注ごとに個別に1梱包ずつ荷物を集めてくる方法である。別名で「摘み取り方式」とも呼ばれている。シングルピッキングのメリットは作業内容が単純であるため、アルバイトやパートの未経験者でもミスすることなく、作業を任せることが可能である。一方、デメリットとしては作業スタッフは1つの受注ごとに移動するため、作業員の移動距離が長くなる。
トータルピッキング
複数の受注に対して種類ごとに品物を集めた後、最後に仕分けする作業のことである。別名で「種まき方式」とも呼ばれている。トータルピッキングのメリットは複数の商品を1度に集めるので作業員の移動距離も少なく、作業時間の短縮が可能である。一方、デメリットとして振り分け作業が必要なため、慣れない作業スタッフは作業ミスが発生する恐れがある。
物流KPI
KPIとは「Key Performance Indicator」の略語で日本語にすると「重要業績評価指標」と訳される。物流KPIとは、企業の物流業務を取り巻く経営状況を把握するための、生産性、コスト、品質等のKPIを意味している。
昨今、物流業界では燃料費の高騰やドライバーの不足等により、企業間競争が激化しており、価格競争に陥らない手法が必要不可欠な状況となっており、2005年に国土交通省は業界の経営健全化のため「物流事業者におけるKPI導入の手引き」を発行して物流KPIの活用を促している。
物流KPIを導入することのメリットは、業務改善には問題点の発見が必要不可欠だが、KPIを活用することで「容易に問題点を可視化できる」ことが挙げられる。
また、KPIを活用することで数値化されたデータをすぐに社内で共有化することができ、社員同士のコミュニケーションが活性化できる。
さらにKPIは客観的なデータであるため、この結果、従業員のモチベーション向上も期待でき、合理的で公正な評価が可能となる。
フルフィルメント
フルフィルメントとはECサイトや通信販売等で顧客が商品を購入してから商品を受け取るまでの一連の業務プロセスを指す。具体的な業務としては注文受付、入荷・検品、ピッキング、梱包、発送、商品管理、問い合わせ対応までの広範囲を担当する。語源は英語の「fulfillment」で日本語に訳すと「達成」や「実行」を意味する。
一般的にWebサイト構築や顧客分析等のマーケティング領域はフルフィルメントの領域外となっている。類似用語に3PL(サードパーティーロジスティクス)があるがフルフィルメントとは対応範囲が異なる。具体的に3PLは物品の物流業務に限定した領域を代行するのに対してフルフィルメントは注文受付から商品受け渡し後の問い合わせ対応までの広範囲を代行する。なお、フルフィルメントサービスを導入することで「業務効率化」と「顧客満足度向上」の点でメリットが得られる。
たとえば、一連の物流業務の実施においては、多くの人員の配置や自社顧客対応のノウハウが必要となるが、フルフィルメントサービスの導入により、自社業務の効率化を図りつつ、受注から配送までの時間短縮・コールセンターのきめ細やかな対応を実現し、結果として顧客満足度向上に繋げられる可能性がある。
ま行
マテハン
マテハンは、マテリアル・ハンドリング(Material Handling)の略称であり、機械を使用して荷物の運搬や積み下ろす「荷役作業」を指す。倉庫内において、重労働を含む物流作業の安全性の向上と効率化のための機器をまとめて「マテハン機器」と呼ぶ。
コンベヤ・フォークリフト・パレットなどもマテハン機器に含まれる。現代はマテハン機器のIT化が進み、AIが搭載された無人搬送車(AGV)による荷物の運搬作業、天井から吊したアームを利用して畳んだ状態のダンボール箱の組み立てから、仕上げのテープ貼りまですべて自動で行う「自動製函機(ケースフォーマー)」が代表的だ。
マテハン機器は人手不足の解消および人件費の削減、倉庫内における事故の軽減などのメリットが挙げられるが、機器の故障時のトラブル対応や、作業が広い範囲にわたって止まってしまうなど、機器への依存度を強め過ぎないよう注意が必要である。対策としては、機器の故障時の対応マニュアルやエンジニアの現場常駐などが検討されることが多い。
A-Z,0-9
AGV
AGV(Automated Guided Vehicle)は「無人搬送車」を指す。倉庫内の生産ラインなどで、コンピューター制御により自動運転される車両である。台車のほかに無人で荷物の搬送や荷役が行えるフォークリフトもAGVの中に含まれる。軌道があるタイプと無軌道のタイプがあり、軌道のタイプは、あらかじめ床に敷いたレール上のみ走行できる。無軌道タイプは、初めにルートを定めておけば、レールがなくとも自由に倉庫内を走行できる。
一方で、次世代AGVとして注目を集めているAMR(Autonomous Mobile Robot)は、周りの環境や障害物を感知し、自ら迂回経路を作成して目的地まで移動できる「自律走行搬送ロボット」である。
AGVは「車両」でAMRは「ロボット」という違いはあるがどちらも、従業員の負担軽減および人手不足の解消、物流作業におけるミスを減少につなげられるというメリットがある。AGVの歴史は古く、1980年代からすでに活用されており、当時は磁気テープを床に敷き、リニアモーターカーのように磁力を用いた方法で動かす軌道タイプが主流だった。
AMR
AMR(Autonomous Mobile Robot)は「自律走行搬送ロボット」を指す。自ら周囲の状況や障害物を把握して目的地まで移動するロボットであり、途中に障害物や通行止めとなっている通路があった場合は、迂回して目的地までの最短ルートを導き出す。従来の物流においては、荷物の運搬および荷役ができるロボットといえばAGVが主流だったが、ガイドの設置および障害物があった場合の臨機応変な対応ができないというデメリットがあった。一方、AMRであれば通行するためのガイドが必要なく、基点と現場のジョブさえ設定すれば、自ら繰り返しルート変更が可能である。
さらにAMRは優れた耐荷重性を有しており、数百キログラムから数千キログラムまで運搬が可能な製品も存在する。また専用端末を用いた遠隔操作が可能なため、作業中に必要な部品を持ってきてもらうなど効率を重視した対応ができる。AMRの導入により、従業員の負担軽減および倉庫内における事故の減少、さらに物流業務の正確性が向上すると期待されている。
DC
DC(ディストリビューションセンター)は「Distribution Center」の略語で日本語にすると「在庫型物流センター」である。DCは商品が入荷すると検品後に一時保管。その後、顧客からオーダーが入るとピッキング、梱包等を行い、商品を出荷する拠点である。
DCの特徴として荷物を在庫する機能を持つ。このため、DCは顧客への迅速な対応が求められる卸売業や製造業での活用が多い。なお、物流センターの種類はDCとTC(トランスファーセンター)の2タイプある。DCは商品の在庫を持つ「在庫型物流センター」であるのに対してTCは、商品の在庫を持たない「通過型センター」である。
DCは拠点内に商品の在庫を保有するため、需要が急増しても顧客を待たせることなく、商品の出荷が可能なことが代表的なメリットだ。一方、デメリットとしては在庫を保有する場所や設備が必要なため、管理コストが増加する。
LMS
LMS(Logistics Management System)は「ロジスティクスマネジメントシステム」といい、製品や部品の仕入れから顧客の手に渡るまでの商品物流を一括管理するためのシステムを指す。入荷管理・倉庫内の在庫管理・出庫管理が行え、物流全体にかかるコスト計算が可能なシステムも存在する。
これまで、市場における価格やニーズの変動は激しく、製品の在庫や人材のコントロールが的確に行われないなどの問題があった。しかしLMSの活用により、倉庫内だけでなく複数拠点や車両の位置など、現場外を含めた全体の状況の可視化ができる。
またサプライチェーンにおいて必要なリソースも、システムがあらかじめ算出してくれるため、ムダのない物流運用が可能となる。WMS(倉庫管理システム)としばしば混同されることがあるが、WMSはあくまでひとつの倉庫内を中心とした物流管理が行えるシステムである。一方でLMSは1つの企業を中心とした物流全般の管理が行えるシステムを指す。つまりLMSなら、企業と関連する複数の拠点における、全物流の管理が可能となる。
RFID
RFID(Radio Frequency IDentification)とは「自動認識技術」を意味する。RFIDは日常生活における身近な技術であり、鉄道へ乗る際に利用する「Suica」や「Pasmo」などにもRFIDの要素技術が利用されている。
BtoB領域の物流においてもRFIDは広く用いられている。たとえば、製品や部品にICを組み込んだプレートやラベルを貼り、専用の機器で読み取ることで、箱の中身や位置情報の登録、データの読み書きや更新が非接触でできる。
一度に複数のICタグが読み取れることから、ピッキング作業や荷物の情報更新において大幅な時間短縮および作業効率が向上する。
またICタグは複製が非常に困難であることから、セキュリティ性能にも優れ、寿命が長いため繰り返し利用できる。RFIDの最大の特長は、荷物を移動させたままICを読み取ることが可能な点だ。ベルトコンベアで流れている荷物の読み取りも可能なため、物流における作業効率が大幅に向上する。
RFIDは倉庫以外においても、港湾からコンテナを出荷する時に含まれている荷物の情報伝達などで大幅な時間短縮を実現している。
TC
TC(トランスファーセンター)は「Transfer Center」の略語で日本語にすると「通過型物流センター」と呼ばれる。TCは各所から入荷した商品を在庫することなく、仕分けて素早く出荷する物流センターである。
TCの特徴として在庫を持たないため、コンビニエンスストアなど少量で頻繁にかつ多店舗の出荷に適している。物流センターの種類はTCとDC(ディストリビューションセンター)の2タイプがある。TCは商品の在庫を持たない「通過型物流センター」であるのに対して、DCは、商品の在庫を持つ「在庫型センター」である。
メリットは拠点内に商品の在庫を持たないため、大規模な保管場所や管理設備などが不要となる。この結果、設備利用費や人件費を削減することができ、さらに不良在庫を抱える心配が無くなる。一方、デメリットは商品在庫を持たないことから需要の急増に即対応できない場合がある。
TMS
TMS(Transport Management System)は配送状況や配送スケジュールなど、倉庫外における製品や部品の状況をリアルタイムで把握して管理できるシステムのことで、輸配送管理システムとも呼ばれる。TMSを活用すれば、以下のような機能が利用できる。
車両管理
配送に携わる車両において自社で保有しているなら車検情報から定期検査日、稼働日などが一覧で管理できる。またリース契約の車両も、契約先情報およびリース料金のシミュレーションも可能。
配車管理
地図に表示された製品や部品を積んだトラックの位置情報や配車ルートが確認できる。さらに各トラックの積載量が一目で把握できるため、適切な分配が容易になり作業量過多などを防げる。
運賃計算
製品や部品の配送にかかる運賃の計算が可能になる。休日の割増料金や高速道路を利用した場合など、さまざまなパターンを混ぜながらコスト計算ができる。
運賃支払
運賃計算から出た結果を見積書へ反映して作成、または実際にかかった費用の請求書を作成して送付できる。
WCS
WCSは「Warehouse Control System」の頭文字からなる名称で「倉庫制御システム」を指す。制御対象は倉庫内にある設備やシステム全般であり、たとえば、マテハン機器やコンベア機器、IoT機器など機械の稼働率や動作情報などがリアルタイムで監視できる。またロボットアームやコンベアに遠隔操作指示を出すことも可能。さらに、機器や設備の故障や不具合時のお知らせ、ソフトウェアの自動更新にも対応できる。
WCSを活用することで効率よく機器の稼働が行えるため、省エネ効果や製品の先入れ先出し化の管理が容易になる。さらに倉庫内の一部の業務を自動化させることができ、人材不足問題の解消や人件費削減の効果が期待できる。またWCSが管理・制御できる対象はあくまで倉庫内部の設備および機器のみであるため、従業員は含まれない。
WES
WESは「倉庫運用管理システム」とも呼ばれ、主に倉庫内におけるリソースや作業量の管理と制御を補助するシステムである。AGV機器や倉庫内で使用されているIoT機器の一括制御が可能で、稼働中機器の可視化や稼働率の数値化が行える。
またデータの入力作業や配送ルートのプランニングなどが自動で行えるようになるため、物流における業務の効率化にもつながる。ウェアラブル端末を用いれば、現場において離れた場所にいる従業員に対して、システムが算出したデータに基づき、的確な音声指示が出せる。倉庫内における補助システムとしては「WCS」と混同されやすい。
倉庫管理システムWMSとの違いは、WMSは倉庫内における作業の可視化や効率化の実現が可能だが、WESのように倉庫内の機器制御はできない。またWCSは倉庫内の機器制御はできるものの、倉庫内における作業の可視化や効率化はできない。つまりWESは、WMSとWCS両方の特徴とメリットを兼ね備えたシステムといえるだろう。
WMS
WMSは「倉庫管理システム」と呼ばれ、製品や部品を倉庫へ入庫してから出庫するまでの一連の流れを管理するためのシステムだ。機能は入庫管理やラベル・バーコードの発行など多種多様だ。そのなかでもとくに必要とされる機能をひとまとめにしてカスタマイズにかかるコストを削減した製品を「パッケージ型倉庫管理システム」という。
入庫管理
倉庫へ入庫する製品や部品の名称と個数および入庫スケジュールがクラウド上で管理でき、インターネットに接続できる端末からいつでも閲覧できる。
ラベルやバーコードの発行
倉庫へ入庫させた製品や部品を識別するためのラベルやバーコードが発行できる。
在庫管理
発行したラベルやバーコードを専用端末で読み取ることで製品や部品の在庫管理が行えるうえ、情報はWMSのシステム内に保存および更新できる。
棚卸管理
倉庫内に保管してある製品や部品の状況を、一覧表を表示させることで一目で把握できる。
出庫管理
ピッキングリストを作成し、出庫する倉庫内の製品や部品を管理できる。またラベルやバーコードを読み取りながら出庫作業を行うことで、出庫漏れを防ぐことにつながる。
なお、WMSパッケージは一般的にオンプレミス型とクラウド型の2種類が提供されており、自社倉庫用にカスタマイズする場合はオンプレミス型を選択し、既存の機能や操作でも支障がない場合はクラウド型を選ぶことが一般的である。
3PL
3PLとは、第三者(サードパーティー)が荷主に代わって物流の業務を一括で請け負う業態である。3PLは「Third Party Logistics」の略語で日本語にすると「第三者による物流の最適化」と訳される。サードパーティーとは物流を担当する企業を指し、ファーストパーティーは製品の製造を担当するメーカー、そしてセカンドパーティーは製品の販売を担当する小売業者を指す。なお、3PLを担う企業はアセット型とノンアセット型の2種類に分類される。
アセット型
アセット型は自社で保有する資産(トラック、倉庫施設、システム等)を駆使して物流サービスを提供する企業のことである。この型は自社資産を保有し物流全般を請け負うことからファーストパーティー、セカンドパーティーとの協力体制を構築しやすいというメリットがある。
ノンアセット型
ノンアセット型は自社で資産を持たず、外部業者を活用して物流サービスを提供する企業のことである。この型のメリットは自社資産を保有しないため、物流コストを抑えたいケースで有効である。