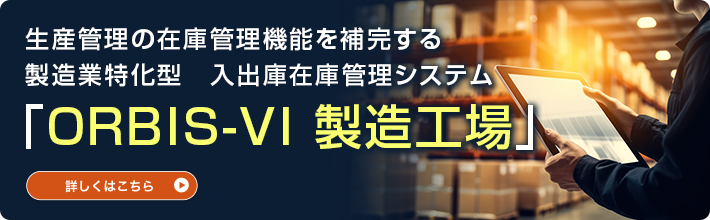倉庫管理における5つの課題と解決例

「倉庫の入出荷物量が増え、Excel管理が煩雑になった…」「繁忙期にシステムがパンクしてしまう…」といった問題はありませんか。物流インフラを支える倉庫の業務は、ニーズに大きな変化が見られるようになりました。それに伴い、業務内容やシステムにも新たな課題が生まれています。
倉庫管理で抱える課題は、事業の規模や業態、事業展開の違いによってさまざまです。そこで本記事では倉庫業務で発生する代表的な課題を5つご紹介するとともに、それぞれの課題に対して解決した事例をご紹介します。
目次
倉庫管理業務・システムにおける課題とは
現在の倉庫は単に商品を保管するだけでなく、物流工程を管理する物流センターの役割が求められています。またコロナ禍の影響で店舗での販売がECにシフトし、小売とECが融合する「OMO(Online Merges with Offline)」の取り組みを行う企業が増えました。OMOは、店舗とECをシームレスに連携させることでお客様との接点を増やし、体験価値を向上させるという取り組みです。百貨店やブランドショップがECサイトを開設し、デジタルの販売チャネルを強化していることも後押しとなり、物流の小口多頻度化が急速に進行しています。
経済産業省が2022年9月に発表した「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によると、貨物1件あたりの貨物量が過去20年で半減しています。一方で物流件数はほぼ倍増するという結果となりました。物流の小口多頻度化が加速し、倉庫内の作業量が大幅に増加していることが伺えます。
また日本国内の人口が減少し、労働の担い手も不足しています。40年後の労働人口は現在より4割減少すると予測されている中、アルバイトや外国人スタッフを活用し、ベテラン担当者だけに頼らない仕組みを作らなければ、人手不足を解決できない状況です。
さらに日本の市場が縮小傾向にあることから、海外の販路を開拓し倉庫の拠点を置く企業も増えています。言葉の壁、文化の壁を乗り越えて情報を共有することが新たに求められます。
倉庫業務では、こうした社会環境の変化からさまざまな課題を抱えています。どのような課題があり、どう解決していけばよいのでしょうか。ここでは代表的な5つの課題と、それぞれの解決策の事例をご紹介します。
課題①
Excelをベースとした在庫管理に限界を感じる
Excelは事務作業で日常的に使うツールです。倉庫業務においても活用できる無料のテンプレートがインターネット上で出回っており、手軽に管理できるツールとして重宝されています。しかし、Excelは表計算ソフトで高度な管理ができるツールではないため、長く運用を続けているとさまざまな問題が発生することがあります。
まず、Excelは簡易的にデータを保持するだけで、データの整合性を保つための入力チェックには限界があります。またExcelでどのように管理するかは担当者に依存する傾向にあります。そのため「担当者が設定した関数が複雑で他の人が修正できない」「担当者のPCにあるファイルにリンクしているため、他の人が参照できない」といった問題が発生します。さらにExcelファイルを参照したり、更新したり、といった作業は事務所に戻らないとできないため、リアルタイムで最新状況が把握できないという問題もあります。
WMS(倉庫管理システム)の導入で、Excel管理の非効率性が解消
Excelによる在庫管理からWMS(倉庫管理システム)にシフトすることで、業務上抱えていた問題が解決しました。業務が標準化され適切な入力チェックがシステムで行われるため、業務効率が大幅に向上しています。ロケーション別の在庫が最新の状態で参照できるため、商品が置いてある棚や空いている棚を探す必要がなくなり、作業時間が短縮できました。
課題②
繁忙期に急増する物流トランザクションに対応できない
従来のWMSは、どの企業でもデータセンターや自社の構内に構築するオンプレミス環境で運用するのが主流でした。繁忙期と閑散期の差が激しい物流業務では、オンプレミスにおけるITリソースの有効活用が課題になります。最近ではECの活性化で物流トランザクションが拡大したために繁忙期の作業量にサーバーのスペックが対応できなくなり、システムが停止するというトラブルも発生しています。またオンプレミスではITリソースの拡張にも手間がかかるだけでなく、拡張すると閑散期にITリソースにムダが生じるのが課題です。さらに長く運用するには時代に合った作業の効率化が求められますが、オンプレミスのアプリケーションでは機能拡張にも問題がありました。
WMSをクラウド環境に移行し、繁忙期のみITリソースを増強
WMSをクラウド環境に移行することで繁忙期のトラブルがなくなりました。オンプレミスは拡張するのにもコストがかかりますが、クラウド環境は繁忙期だけスペックを拡張することができるため、ITリソースを効率よく活用できています。
またクラウド環境に構築したことで、ハードウェアやネットワークはクラウドサービス事業者が運用・保守を担当するため、運用・保守の費用が削減され、運用・保守担当者の一部を別の仕事に振り分けられるようになりました。さらにWMS開発元の積極的な投資により短いスパンで機能拡張が行われているため、利便性が高まりました。
課題③
ベテラン担当者と新人担当者の業務効率の差が大きい
人手不足が深刻になり小口の出荷量が増える中で、作業の効率化と工数削減、作業精度の向上は避けて通れない課題です。倉庫作業は、担当する従業員の進め方やスキルに依存する部分が大きいと言われています。そのため新人が入った途端、作業スピードが目に見えて落ちるといった経験をした方も多いのではないでしょうか。作業量が増えた場合担当者を増やす必要がありますが、新人担当者の教育に時間がかかり、効率化ができないという問題があります。
一方でベテランの担当者は自己流で作業することがあり、ミスを誘発するという問題もあります。自身の経験やスキルを過信して、慢心するといった要因が考えられます。自己流から脱却し作業精度を高めることも大きな課題です。
庫内作業のサポート機能や労務管理機能で人的リソースの効率性を向上
庫内作業の効率化を目的として新たなWMSを導入。導入したWMSは経験の浅い担当者でも作業を効率化できる工夫や作業精度の向上を促す仕組みが搭載されています。たとえば倉庫のロケーション、在庫、オーダーの動きをビジュアル化できる機能があるため、作業担当者が倉庫内をどのように動けばよいのかがわかり、作業精度の向上が期待できます。また作業担当者をどのように配置すればよいか、合理的な判断が可能になりました。
さらに、作業に対して標準時間を設定し各担当者の作業状況を追跡することで、適正な人員は何人か、どの部分が非効率になっているか、非生産的な作業にどのくらいの時間を費やしているか、といった情報を迅速に把握できるようになりました。
課題④
国内・海外の倉庫・拠点の統合管理が難しい
グローバル化が進み、海外に進出する企業が増えています。国内と海外の拠点を持つ場合、使用する言語やタイムゾーンの違いから、それぞれにシステムを導入する企業が多かったのも事実です。その場合各システムは現地の言葉で運用・管理されているためブラックボックス状態となり、内部統制に課題が残ります。また外貨建てで残高管理ができない、システムが分かれているためにリアルタイムに状況を把握できないという問題もあります。
国内・海外倉庫を一括管理できるWMSを導入し、グローバルで情報を共有
国内・海外に倉庫を展開しているグローバル企業では、各倉庫を国内外問わず一括管理できる機能を持つWMSを導入することで解決しました。多言語に対応しているため、担当者に合わせて言語の表示が変わり、どの海外拠点でもシームレスに管理できます。一元的に管理する仕組みを備えつつ、各国の仕様に合わせた設定が可能になると、現地での運用がしやすくなります。さらに現地サポートを提供しているソリューションであれば、導入もスムーズです。
課題⑤
3PL事業者では複数の荷主の倉庫管理・請求処理が煩雑になっている
物流部門を代行し高度な物流サービスを提供する3PL事業者は、物流効率化によるCO2削減や地域雇用の創出が期待されています。国土交通省でも各種支援を実行し、3PL事業を総合的に推進しています。3PL事業者特有の課題としては、複数の荷主の異なるニーズに対応する必要があるということです。食品の賞味期限、化粧品の製造日、ロット管理など、扱う商品によって管理方法が異なるため、倉庫管理や請求処理が煩雑になっているという問題があります。
3PL業務対応のWMSを導入し、荷主ごとの管理が簡単に
同様の問題を抱えていたある企業では、3PLの業務に対応したWMSに移行しました。こうしたWMSでは、荷主からのさまざまな要望に対応し、状況を一元管理する仕組みを備えています。複数の荷主それぞれが取り扱う商品の特性に合わせた管理をより正確にできるようになりました。さらに保管料や荷役料等を集計して請求書を発行する機能が提供されていたため、請求業務を効率化できています。
倉庫作業を効率化するWMS(倉庫管理システム)の活用
倉庫業務に課題を抱えているなら、現状に合ったWMSを選ぶことで倉庫作業を効率化でき、費用対効果を最大限に引き出すことができます。NSWは長年にわたる物流システムの開発実績を持ち、多様な業態に応じた入出庫・在庫管理のノウハウを持っています。これまで多くのお客様の倉庫業務内容に応じて最適なソリューションを提供し、導入をサポートしてきました。
小~中規模倉庫向けのWMSとしてオススメなのが入出庫在庫管理システム「ORBIS-Ⅵ倉庫管理」です。入出庫処理、ピッキング、ロケーション・在庫管理といった基本機能のほか、マテハン機器連携機能や生産管理システム連携機能も備えています。また荷主への保管料請求が発生するビジネス向けの機能として、さまざまな請求業務や運賃計算に対応しています。
大規模倉庫や海外拠点を持つ事業者にオススメのWMSがクラウド倉庫管理システム「Infor WMS」です。全世界60か国以上で採用されており、多言語対応やタイムゾーン管理を備えています。倉庫内を3D化して視覚的にモニタリングできる機能も搭載されており、ロケーション、在庫、オーダー、作業員の移動パスを数値化して見える化し、人員を最適に配置することが可能です。
また、クラウド環境にORBIS-Ⅵ 倉庫管理やInfor WMSを構築することで、繁忙期の一時的な処理の負荷にも柔軟に対応し、閑散期のコストを下げることで全体的なコスト効率化が期待できます。
今回ご紹介したような課題をお持ちの方は、ぜひ一度NSWにご相談ください。課題に合ったソリューションを提供し、スムーズな運用をサポートします。
オススメの関連サービス
オススメのアイデアノート